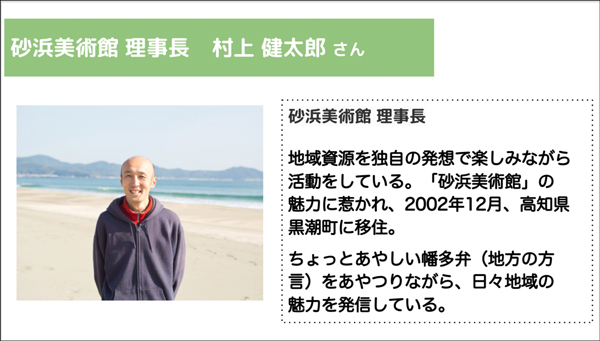N中等部ブログ
【秋葉原】ビジョンの作り方、マインドフルネス
砂浜美術館ゲストを迎えたさまざまなワークショップで新たな価値創造を育む
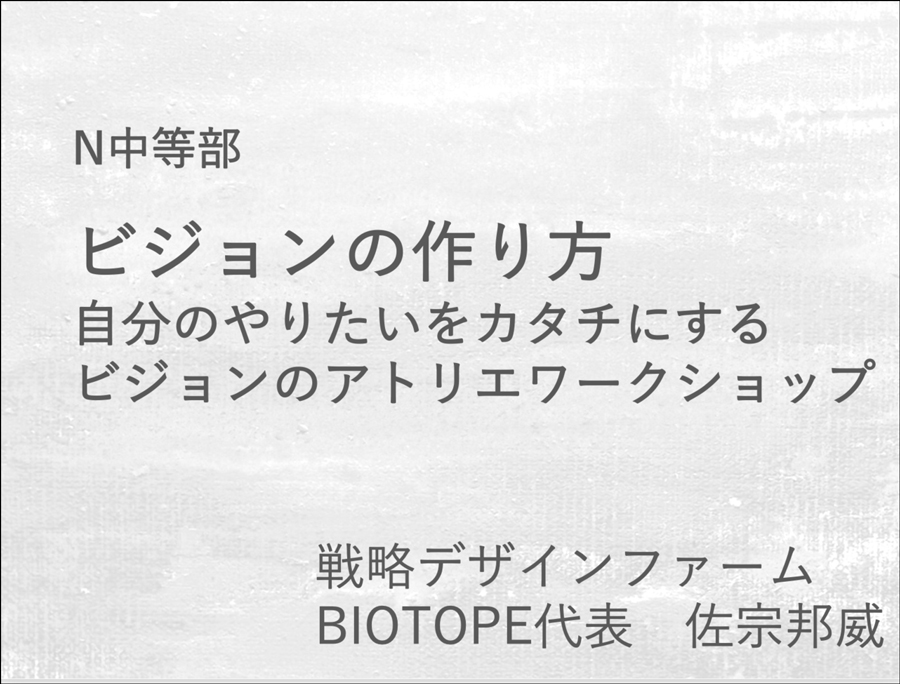
N中等部では、課題解決型授業「PBL(プロジェクト学習)」や「特別授業」などで、各界で活躍している著名人をゲスト講師に迎えたワークショップを行っています。今回はビデオ会議システム「Zoom」を活用して実施した3つの講演の内容を紹介します。
■「ビジョンの作り方〜自分のやりたいをカタチにするビジョンのアトリエワークショップ〜」
1月19日(水)、N中等部秋葉原キャンパスで「ビジョンの作り方〜自分のやりたいをカタチにするビジョンのアトリエワークショップ〜」が開催されました。
ゲストは、株式会社BIOTOPE代表/チーフ・ストラテジック・デザイナーの佐宗邦威さん(※1)。今回の講演は、21世紀型スキル学習で学ぶスキル「思考法」をより深く理解するための合同授業として開催されました。
※1 東京大学法学部卒。イリノイ工科大学デザイン学科(Master of Design Methods)修士課程修了。独立後はさまざまな企業・組織のイノベーション支援を中心に活動。著者に『21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由』など。大学院大学至善館准教授、京都造形芸術大学創造学習センター客員教授も務める。
本授業は、講演、ワークという順序で行い、講演では「ビジョン=夢をカタチにする」方法を教えていただきました。
夢は語るだけでなくカタチにすることが重要であること。未来につくりたいものを妄想し、実際に描いていくことがその一歩になること。手を動かしながらカタチにしていくという、“夢をデザインするための思考法”について学びます。
ワークでは色鉛筆を使ってスケッチブックにデザインをしました。まずは「あなたはどんな動物に似てると思いますか?」というテーマでスケッチを練習。自分に似た動物を考え、その動物をスケッチしていくというワークです。
また、夢を引き出す「妄想インタビュー」のワークをペアになって実施しました。「最近一番ワクワクしたことは?」「あなたが無人島に新しい国を作れるとしたら、どんな国を作りたいですか?」など、ワクワクする質問を交互に質問。言葉にすることで、いつかやってみたいこと”“夢”のイメージが具現化されていきます。
そのインタビューをもとに「あなたがドラえもんのひみつ道具をつくるとしたら?」をテーマにしてスケッチブックに絵を描きました。


ここで言うひみつ道具は、作品内に登場するひみつ道具ではなく、自分が考えたオリジナルのもの。
ひみつ道具=モノという枠にとらわれず「右手を付け替えるとめちゃめちゃ絵が上手くなる」など、人体を強化するアイデアをスケッチする生徒もいました。
最後に作品に名前をつけて完成です。完成後は同じテーブルの生徒とシェアタイム。こだわったポイントを説明し、お互いの作品の感想を伝え合いました。

■社会でどのようにマインドフルネスが活用されているかを知る
角川ドワンゴ学園では、生徒が社会で自分らしくより良く生きていくスキルを身に付けるためのプログラムを数多く実施しています。
その一環として、2月7日(月)に、ヤフー株式会社でマインドフルネスを活用した社内研修を行っているチーム「マインドフルネス・メッセンジャーズ」(※2)の方々にお越しいただき、オンラインによる特別授業を行いました。
※2 日本企業の中でいち早くマインドフルネスを導入したヤフー株式会社。2016年夏からマインドフルネスのメソッドを取り入れた、メタ認知トレーニングをスタート。社内研修だけではなく、社外への講演、体験会も積極的に行っている。
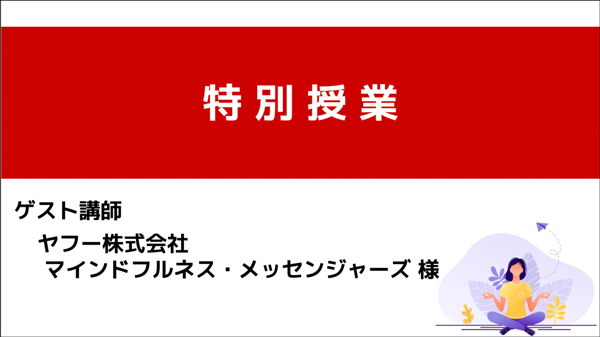
授業は「Yahoo! JAPANについて調べてみよう」という個人ワークからはじまりました。
検索サービスの「Yahoo!検索」だけでなく、ヤフー株式会社について調べ、記事をSlack(角川ドワンゴ学園で使用しているコミュニケーションツール)に共有する生徒も。個人ワークのあとはマインドフルネス・メッセンジャーズの方々による講演です。
N中等部でも取り入れているマインドフルネス(※3)。
※3 自分の今の心の状態に意識を向けることで気持ちを整える手法のこと。N中等部通学コース・ネットコースの「はじまりの会」では、集中力、学習能力、ストレス軽減など目的に、マインドフルネスの呼吸法を取り入れています。
「人間はいつも過去と未来に意識を向けがちです。今、思っていることにあえて意識を集中させるため、マインドフルネスを活用しています」
ヤフー株式会社でマインドフルネスを活用している理由、さらにマインドフルネスが社会でどのように活用されているかについてお話をうかがいました。
説明を聞いた生徒たちからは「確かに!」「今思っていることにわざわざ意識を向ける機会ってあまりないかも」などの感想がSlackの専用チャンネルのチャット欄にリアルタイムで書き込まれていきます。
マインドフルネスの効果を改めて知り「マインドフルネスってやっぱりすごい!」「得することがたくさんあるんだなあ」など、ポジティブな感想が寄せられました。
■NPO法人 砂浜美術館 村上健太郎さんによるトークセッション
最後に「SOWZO」(※4)の授業で行われたトークセッションを紹介します。
PBLの価値創造のプログラムのパート「SOWZO」で、週5コース(※5)の生徒が取り組んでいる「オリT〜自分なりのリーダーシップを活かしながらオリジナルTシャツをデザインしよう」。
※4 PBLには課題解決のプログラム「QAIKETSU」、価値創造のプログラム「SOWZO」のふたつのパートがあります。「SOWZO」は“意味のイノベーション”の考え方をもとに、自分の好きと思う気持ちや願いから新しい価値をアウトプットするプロセスを学ぶトレーニングです。授業内容は年度によって異なります。
※5 N中等部の通学コースは週5日・週3日・週1日の3つの通学スタイルを用意しています。
本カリキュラムでは、グループに分かれ、一人ひとりがリーダーシップを発揮させながら、1つのTシャツデザインを完成させていきます。砂浜美術館で開催される「第34回Tシャツアート展」(※6)への出品が目標です。
※6 「Tシャツアート展」は「写真・絵画展は室内でするもの」という考え方を無視した世界ではじめての美術展。キャンバスにみたてたTシャツに作品をプリントし、浜辺に杭を打ち、ロープを張り、洗濯物を干すように並べていきます。砂浜一面に並んだTシャツは、ひとつの「現代芸術」として完成します。「第34回Tシャツアート展」は2022年5月1日(日)〜5月5日(木)に開催予定。


砂浜美術館とは「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です。」というコンセプトのもと、高知県黒潮町にある長さ4kmの砂浜を頭の中で美術館にみたてた、建物のない美術館です。
波の音、月の光。砂浜に流れ着く漂流物、砂浜についた鳥の足跡、産卵のために訪れるウミガメ、土佐湾を泳ぐニタリクジラ……砂浜美術館のBGM・作品は地域の資源や風景。地域資源を少し見方を変え、新しい価値を生み出す活動で、世界中から注目を集めています。
村上さんは砂浜美術館の魅力に惹かれ、2002年12月、高知県黒潮町に移住。現在は砂浜美術館の理事長として、日々地域の魅力を発信しています。
講演は砂浜美術館の紹介からはじまりました。砂浜を舞台にしたTシャツアート展の映像が流れると、Slackの専用チャンネルのチャット欄に「綺麗!」「いつか行ってみたい!」などのコメントが書き込まれていきます。
砂浜美術館は、もともとは町役場の若手の職員によってはじまったプロジェクトでしたが、当初は地域の一部の方から反対意見もあったそうです。
「30年以上作品を飾り続け、いつしか町を代表するイベントになった」というお話を聞き、「30年以上続けるってすごい」と生徒たちからは驚きの声が上がっていました。
講演を聞き終えた生徒たちは、Tシャツ作りへのモチベーションがより高まった様子。その後の授業では、グループ内で積極的に話し合いながらワークに取り組んでいました。
さまざまなゲストをスピーカーに迎えた講演で、社会で活躍する方々の声を聞いたり、質問をしたり。自分自身の感性と社会の課題を結びつけながら、生徒たちは“自分のやりたいこと”や、新たな価値創造の学びを深めています。